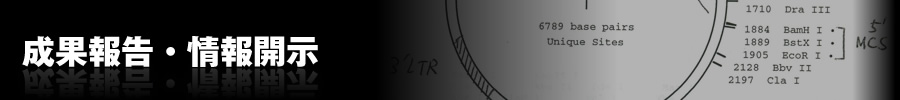

医学系研究科 細胞組織学分野の北田容章准教授が、「日本顕微鏡学会奨励賞(生物系応用研究部門)」を受賞しました。本賞は顕微鏡ならびにそれを用いた研究の進歩に寄与する顕著な研究を発表し、将来の発展を期待しうる若手研究者若干名に年1回授賞するものです。顕微鏡法基礎、生物系応用研究、物質系応用研究、の3部門からなりますが、当部門の受賞者は数年ぶりという快挙でした。授賞式は、5月15日、つくば国際会議場にて行われました。
※本ページの画像は、クリックすると拡大してご覧いただけます。
受賞題目: 形態学を基盤とした生体内在性幹・前駆細胞の同定とその機能解析
受賞理由:
北田先生は、光顕・電顕レベルの顕微鏡学とレクチンなどを用いた組織細胞化学の手法を駆使して、生体内幹細胞・前駆細胞の同定と機能解析の技術を確立し、再生医療の発展にも貢献する優れた業績を挙げています。特に、脈絡叢上衣細胞が脳脊髄液を分泌するだけでなく、損傷脊髄への移植に際しては、再生軸索を指示するとともに自らグリア細胞に分化すること、また培養系にあっては神経へと分化する前駆細胞でもあることを証明したことが高く評価されました。
一貫して幹細胞・前駆細胞に関わる研究をやっていらしたとか?
私は中枢神経の再生、特に脊髄損傷の移植治療というテーマで京都大学医学部の解剖学教室(機能微細形態学部門)で研究を始めたのですが、当時はどのような細胞がどのような効力を示すのかについて今ほど研究が進んでいませんでした。様々な観点から様々な細胞が用いられていましたが、そもそも研究を開始した当初は、神経系に幹細胞が存在するという話が広く知られるようになる前でしたので、幹細胞を用いるという概念はありませんでした。ところが、移植した細胞が何か別な細胞に形態変化し神経再生を助ける方向に機能している、ということが示唆されるデータが得られたので、そこから幹細胞とか前駆細胞というものに興味を持ったわけです。また、当時京都大学医学部には脊髄損傷研究で有名な川口先生という方がいらして、胎児組織を移植することで脊髄が再生するというお仕事を出していらっしゃいました。その意味で、若い細胞が持つ能力に興味を持っていました。成体(アダルトの動物)と言えども脊髄組織には幹細胞・前駆細胞がそもそも存在するわけでして、そうした細胞を人為的に操作して、自分の欲しい細胞を欲しい時に欲しい場所に配置することができれば、損傷した組織を再構築することができるのではないか、それにより脊髄損傷を治せるのではないかと考え、研究を進めています。
医学研究の道に進もうと思われたのは?
医学部に入ったそもそもの理由は、救急医療をやりたかったからです。その当時救急医療の先生方がクローズアップされていて、他人の嫌がるようなこうした大変な仕事をしたい、ストイックな生活をしたいと思ったのです。入学後に様々な刺激を受け、6年目の段階では循環器内科か神経内科のどちらかに進もうかと考えました。かたや急性期の患者さんを預かりとても忙しい循環器内科と、じっくり診察を行って診断をつける神経内科とでは大きく違うようにも思えますが、神経内科については、新しい治療法の開発により「治らなかったものが治るようになる」ということを体験できる学問かもしれない、と思ったわけです。結局は神経再生に関する基礎医学の道を選択したわけですが、現在行っている研究は「治らなかったものが治るようになる」ことを傍観するのではなく、自らがそこに携わっていくというもっと積極的な立場で関わる事ができているという点において、医学研究を志した意味があると考えています。
顕微鏡技術はどんどん進歩しています。逆に言うと、当時出来なかったことがいっぱいあったと思うのですが。
私達は解剖学・組織学という形態学に携わってきた人間ですから、脳や脊髄といった生体組織がどう構築されているか、あるいはどのように維持されているか、というところに興味があるわけですね。そうした生体組織の構造を観察するためには、昔は切片を切って目で見ていたわけなんです。それが今では、例えば脳内の特定の構造を生きた状態で蛍光で明るくさせ、それを生きたまま顕微鏡で観察することができるような技術が存在するわけなんです。今後技術の革新で、もっと自分たちがやりたいと思うことがきっと比較的簡単にできるようになり、技術的に示すことができなかったことをもっとスマートな形で示すことができるようになるんじゃないかと思います。
研究を続けていく上で、嬉しいと思えることは?
形態学では形そのものを目で見て確認できるところにその醍醐味があるわけなんです。実験を行い切片を顕微鏡にセットし、観察する。そして芸術のようなまばゆい光をそこに見出した時、「これは誰も見たことの無い、世界で初めて自分が見る絵なんだろうな」と思うと、とても嬉しく楽しいですね。
診療応用の面はいかがですか。
私自身は神経系に興味を持って研究を進めて来ていますが、私達の教室のテーマである骨髄間葉系細胞やミューズ細胞が、臨床応用に近い細胞として注目されています。ミューズ細胞に関しては非常に新しい概念の細胞ではありますが、多方面の先生方からお声掛けいただき様々な動物での様々な疾患モデルにおける移植効果の確認が進んでいます。こうした地道な研究により、ヒトへの臨床応用が視野に入りつつあると言って良いのではないかと考えています。非常に近い未来の具体的な話としては、細胞移植による再生医療になるわけですね。細胞移植治療は、次世代の医療としてきっと実現・発展していく、次世代と言えどももうすぐそこに見えてきている治療法だと思えます。私自身はどちらかと言えば、すぐそこに見えてきている次世代の治療法ではなくて、次々世代というものを目指したいなと思っているんです。具体的には、生体に内在する幹・前駆細胞の賦活化による変性・損傷組織の再生ということになると思います。このテーマに向かって、独自の視点で研究を進めていければと思っています。 多方面の先生方との連携や、また、私よりも若い世代の方々のお力添えもいただきながら、遠くない将来に私の考える次々世代の医療の実現への道筋をつけられるようにしたいな、と思っています。
![]() PDFファイルの閲覧にあたっては、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerは、Adobe社のウェブサイトより無償で入手していただけます。
PDFファイルの閲覧にあたっては、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerは、Adobe社のウェブサイトより無償で入手していただけます。