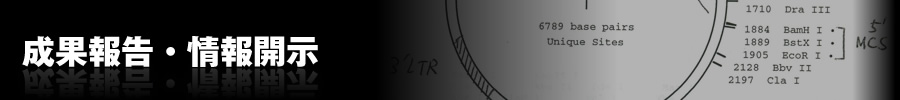

 加齢医学研究所 遺伝子導入研究分野の高井俊行教授が、「平成24年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞(研究部門)」を受賞しました。同表彰は、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた者についてその功績を讃えることにより、科学技術に携わる者の意欲の向上を図り、もって我が国の科学技術水準の向上に寄与することを目的として授与されるものです。表彰式は、4月17日、文部科学省内で行われました。
加齢医学研究所 遺伝子導入研究分野の高井俊行教授が、「平成24年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞(研究部門)」を受賞しました。同表彰は、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた者についてその功績を讃えることにより、科学技術に携わる者の意欲の向上を図り、もって我が国の科学技術水準の向上に寄与することを目的として授与されるものです。表彰式は、4月17日、文部科学省内で行われました。
※本ページの画像は、クリックすると拡大してご覧いただけます。
業績名: 免疫制御Fc受容体の研究
業績概要:
病原体の毒素を中和し、分解処理する血液中の抗体の重要性は周知である。しかしながら、これのレセプターであるFc受容体がどのように機能するのか、またFc受容体が新規薬剤の開発にとって良い標的となるのか不明であった。
本研究は、Fc受容体のγサブユニットが欠損した動物は抗体による炎症が誘発されないことを発見し、さらにFc受容体IIBが欠損した動物では抗体による炎症が逆に過剰になることを発見した。すなわち、抗体により免疫応答のスイッチが正と負の両方向に押されること、これが炎症性疾患を制御する重要な仕組みであることを世界で初めて示したものである。
本研究により、活性化型および抑制型のFc受容体がそれぞれ治療標的となることを示すとともに、このようなペア型の免疫制御受容体が他にも存在することを示唆したことにより、当分野の研究を著しく活性化し、実際に多くの類似した受容体がいまだに発見され続けている。また疾患治療の観点で、近年盛んに臨床応用されている抗体療法に確固とした理論的根拠が与えられた。
本成果は、抗体を用いた疾患治療、たとえば免疫グロブリン大量静注療法や単クローン抗体療法のさらなる改良や新規治療法の開発に寄与することが期待される。
受賞した時のお気持ちをお聞かせ下さい。 実は書類を提出してから1年くらい経っており、すっかり応募したことを忘れていました。内定の知らせを頂き、かつて書類作成の面などで研究室や事務の方々にお手伝いいただきご苦労をおかけしたので、それが報われたな、よかったなと思いました。また、自分の業績が認められたことも有り難いのですが、自分の中で研究の一つの区切りとして、次のステップに移るきっかけになればいいなと思いました。
実は書類を提出してから1年くらい経っており、すっかり応募したことを忘れていました。内定の知らせを頂き、かつて書類作成の面などで研究室や事務の方々にお手伝いいただきご苦労をおかけしたので、それが報われたな、よかったなと思いました。また、自分の業績が認められたことも有り難いのですが、自分の中で研究の一つの区切りとして、次のステップに移るきっかけになればいいなと思いました。
1992年にアメリカに行かれてこのFc受容体の研究をなさったということですが、当時これをテーマに研究なさろうと思ったきっかけは何だったのでしょうか。
研究領域をいろいろ変えていた時期もあるのですが、元々学生の頃から興味のあった免疫学にその頃から戻り始めていました。丁度「Fc受容体の遺伝子のノックアウトマウスを作る」というプロジェクトに参加しないかという声がかかりましたので是非やらせてほしいと、アメリカに1年ちょっと行って研究しました。それがたまたま上手くいき、しかも結構面白い表現系だったので、日本(岡山大学)に帰ってからも続けました。簡単に言えば免疫を活性化するFc受容体と抑制するFc受容体の2種類あるということがとても面白いなと思いましたので、そのあたりを今後もキーワードとしてやれたらなと思いました。
その時から20年くらい経ちますが、ご苦労とか印象に残っていることがありましたら。
喜んだり悲しんだりは研究の世界ですからいろいろありましたけれども、留学の時には1年ちょっとしか期間がなかったのでこれで失敗したらだめだなと思いながらやっていたという悲壮感もありました。結果として上手くいったので、それはよかったと思います。日本に帰ってからもそれを継続していく中で、若い人たちと一緒にやっていくとか教育という面も含めるととても大変な時期もありました。けれども、若い人たちの協力や頑張りでここまで研究を続けてこられたなというふうに思っています。
今後も免疫病の克服に向けて研究を展開していきたいということですが、先生のご研究は診療にどのように適用されているのでしょう。
PIR-Bの方はまだ診療にはつながっていないのですが、将来的には診断につなげていきたいと思っています。今回の業績のメインであるFc受容体に関しては、抗体は勿論感染症の対抗手段としてとても大事ですし、がんや自己免疫疾患の治療にも使われるということもあります。今とても抗体療法というのが注目されてきています。それは20年くらい前から、製薬会社さんも含めた地道な努力があればこそなのですが、その中で私たちが研究したFc受容体が抗体療法の有効性を理解するのにつながっているのかなというふうには思っています。
最後に学生さんを始め、若手研究者の皆さんへのメッセージをお願いします。
今やっていらっしゃるお仕事に熱中して一生懸命やりさえすれば必ず花開くと思います。是非継続してやっていただければと思います。
![]() PDFファイルの閲覧にあたっては、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerは、Adobe社のウェブサイトより無償で入手していただけます。
PDFファイルの閲覧にあたっては、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerは、Adobe社のウェブサイトより無償で入手していただけます。